缶の履歴書
■リサイクル特性の向上
缶1本に秘められた技術革新
シリーズの第2回目は、工業化以後、約1世紀にわたって私たちの暮らしを支えてきたスチール缶の変遷を、製缶技術を中心に垣間見てみよう。
20世紀初頭に始まった日本の近代製缶業
缶詰容器の条件は、長期保存に耐え、内容物の風味や質が変わらず衛生的なこと。また、容器の供給が安定的で価格が安く、取り扱いが容易で丈夫で美しいことも重要な要素となる。
こうした条件を確実に満たすため、鉄鋼業と製缶業は密接な協力関係の中で、缶素材(鋼板)とめっき法、製缶技術の3つのアプローチからスチール缶の歴史を築いてきた。
いまスチール缶の種類は、3ピース缶と2ピース缶に大別できる。
 3ピース缶は、胴、蓋、底の3つの部品からできた強度の高い缶(接着缶、溶接缶など)。真空度の高い食品缶や非炭酸系飲料に使われている。
3ピース缶は、胴、蓋、底の3つの部品からできた強度の高い缶(接着缶、溶接缶など)。真空度の高い食品缶や非炭酸系飲料に使われている。
一方、2ピース缶は底付きの缶胴、蓋の2つの部品からなる軽量の缶(DI缶、薄肉化深絞り缶、絞り缶など)。円形に打ち抜いた板を絞り加工やしごき加工でカップ状に成形しており、主に食品や内圧の高い炭酸飲料などに使われている(図1)。
近代製缶業の幕開けは、1897年にアメリカで誕生した「サニタリ缶(Sanitary Can:衛生的な缶)」だろう。蓋底を缶胴に巻き締める2重巻き締め法の開発と連続ハンダ付け法の確立があいまって実現したものだ。 ハンダやフラックスが缶内に入らないことが「衛生的」と呼ばれた所以だ。
日本に初めてサニタリ缶の自動製缶機が輸入されたのは1913年(大正2年)。その翌年には長崎水産試験所で「いわしのトマト漬け缶詰」の研究がスタートしたほか、1917年には東洋製罐(株)が創立され、アメリカから導入したハンダ缶と打ち抜き缶の製缶機械によって本格的な缶の工業生産が開始された。日本において製缶事業と缶詰事業が分離し、力強く歩み出した瞬間である。
高価な錫を使用しない技術のブレイクスルー
 缶製品に限らず、リサイクル性をいかに高めるかが問われている容器類。そこで開発されたのが、便利さはそのまま残し、環境にも配慮した金属容器TULC(タルク/Toyo Ultimate Can)である(東洋製罐/写真)。
缶製品に限らず、リサイクル性をいかに高めるかが問われている容器類。そこで開発されたのが、便利さはそのまま残し、環境にも配慮した金属容器TULC(タルク/Toyo Ultimate Can)である(東洋製罐/写真)。
第二次世界大戦前、缶詰はみかんなどの輸出用と軍の食糧として活用されたが、一般家庭ではなかなか口にできない高級食品だった。当時主流だったのがハンダ缶で、大戦後はめっきで使われる防食性の高い錫が希少資源で高価なため、めっき被覆を薄くする電気めっきブリキ法を採用したり、ハンダに含まれる錫を減らすなどコストダウンの努力がなされ、徐々に庶民の生活にも浸透するようになった。
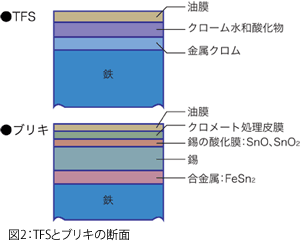 1950年代になると、「オレンジジュース缶詰(1955年/明治製菓)」が登場し、「缶入り飲料」という新たな用途が生まれ、ハンダ缶はビール(アサヒビール)や炭酸飲料(サントリー)、果汁飲料に使われるようになる。その後、海外で鉛の有害性が指摘されたり錫の価格が高騰したことから、ハンダを使用しない低コストの缶開発が望まれるようになった。
1950年代になると、「オレンジジュース缶詰(1955年/明治製菓)」が登場し、「缶入り飲料」という新たな用途が生まれ、ハンダ缶はビール(アサヒビール)や炭酸飲料(サントリー)、果汁飲料に使われるようになる。その後、海外で鉛の有害性が指摘されたり錫の価格が高騰したことから、ハンダを使用しない低コストの缶開発が望まれるようになった。
その製缶技術のエポックメイクとなったのが、1961年、世界に先駆けて生産を開始した鉄鋼材料「ティンフリースチール(TFS/東洋鋼鈑、新日鉄/図2)」による「接着缶(東洋製罐)」の実用化(写真1)と、スイスで高速生産化された「溶接缶」の登場だ。
TFSとは一切錫を使わず鋼板表面を化学処理(クロムめっき)した画期的な材料。これらの技術革新をベースに、飲料缶詰を中心とした大量生産・消費の時代が到来したのである。特に1963年の「コーヒー飲料缶詰」の登場と、レジャーブームによるアウトドアでの需要増大が缶詰の消費量を飛躍的に伸ばした。
飲料缶は鉄 VS アルミの時代に
1970年代になって、ビールや炭酸飲料市場の拡大とともに缶市場を席巻したのが軽量の「DI缶(Drawn and wall Ironing can)」だ。「容器の強度を内圧で保持する」という新しいコンセプトの登場である。
もともとこの技術は1930年代、スイスで絞り・しごき加工で弾丸の薬きょうを製造したことに遡る。1955年にはアメリカのアルミ材料メーカーの需要拡大策として工業化され、1959年、アメリカ・クアーズ社がビール用のアルミDI缶を製缶した。
 日本でも1971年にはアルミDI缶の生産がスタート。鉄鋼業界はそれに対抗して、鋼中の結晶を均一に制御することによって、加工性に優れる柔らかい鋼板を連続的かつ安定的に製造する技術を確立し、当時、深絞り加工が必要なため柔らかいアルミしかできなかったDI缶を、世界で初めて鉄で製造することに成功した(1973年/大和製罐、新日鉄/写真2)。
日本でも1971年にはアルミDI缶の生産がスタート。鉄鋼業界はそれに対抗して、鋼中の結晶を均一に制御することによって、加工性に優れる柔らかい鋼板を連続的かつ安定的に製造する技術を確立し、当時、深絞り加工が必要なため柔らかいアルミしかできなかったDI缶を、世界で初めて鉄で製造することに成功した(1973年/大和製罐、新日鉄/写真2)。
DI缶は世界的に爆発的な人気を呼んだイージーオープン蓋とともに急速に普及し、いよいよ飲料缶における鉄VSアルミの時代が到来した。
スチール缶の世界では、低コスト・軽量化への挑戦が本格化し、現在では1950年頃に比べて約60%の軽量化を実現している。1年間で節約された鉄の量は東京タワーおよそ150本分に相当する。
また現在、飲料缶に限らず材料のリサイクル性が問われる中で、鉄の再利用は人類の歴史とともにあり、工業的な再利用も17世紀には始まっている。
鉄利用の長い歴史と社会秩序の中で、裾野の広いリサイクルの基本的なコンセプトを構築してきたのである。革新的な技術とともに、こうしたスチール缶の優れた特性が、環境の時代である21世紀において改めて再認識されるだろう。
監修/東洋製罐(株)環境対策室 堀口誠氏
参考資料/東洋製罐(株)社内資料ほか
(次回は21世紀のスチール缶の省エネ・環境対策を最新技術とともにご紹介します)

