缶の履歴書
■食の安全が問われる今だからこそ新鮮で美味しい「食料缶」
日本の缶詰の幕開け
日本初の缶詰製造は、1871(明治4)年、長崎で外国語学校の司長をしていた松田雅典が、フランス人教師のレオン・デュリーから製法を教わり作ったイワシ油漬缶詰から始まった。そして1877(明治10)年10月10日、日本初の缶詰工場である北海道開拓使缶詰工場で、初めてサケ缶詰が商業生産された。開拓使は、北海道とその周辺島の行政・開拓を行う官庁として明治政府が設置したもので、缶詰製造は国の産業振興の一環としてスタートした。この日を記念して、現在10月10日は缶詰の日として制定されている。
日清戦争や日露戦争のころは軍用食料として活躍し、その後は輸出産業としても発展していった。1913(大正2)年には、アメリカから自動製缶機械と自動缶詰機械を導入して量産が可能になり、サケ、マス、カニの欧米への輸出が飛躍的に伸びていった。昭和に入ると、戦争の影響で食料および鋼材の調達が困難になったため、一時期は生産が激減したが、戦後、サバなどの青物缶やミカン、マグロ、カニ、サケなどの輸出が順調に伸び、缶詰は日本の輸出産業の大きな担い手となった。1995(平成7)年以降は、輸入品の関税引き下げや自由化、海外からの低価格品が急増し、輸入量が国内生産量を上回っている。
新鮮な美味しさと栄養を閉じ込める生産工程
缶詰はフレッシュではないイメージを持たれがちだが、実際には、最も味が良い旬の食材を使い、すばやく調理・加工して密封している。さらに密封した状態で容器ごと加熱殺菌するため、保存料を添加する必要がない。食料缶には、採れたて、できたての美味しさが閉じ込められている。
現在、特に注目されているのは、魚缶詰に含まれる栄養成分。脳を活性化しコレステロールを下げる栄養素であるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)、カルシウムが手軽に食べられるため、缶詰が見直されている。これらの栄養素は熱に強く、加熱による影響が少ないため、生魚と変わらない栄養素を確保できる。
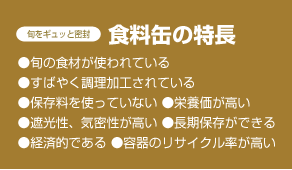 野菜には、熱に弱い水溶性ビタミンが多く含まれているが、これらは液汁に溶け出すため、液汁を調理に使えば栄養素は確保できる。また、食物繊維は加熱により溶けて摂取しやすくなるメリットがある。
野菜には、熱に弱い水溶性ビタミンが多く含まれているが、これらは液汁に溶け出すため、液汁を調理に使えば栄養素は確保できる。また、食物繊維は加熱により溶けて摂取しやすくなるメリットがある。
さらに食料缶は経済的で環境負荷も少ない。冷蔵や冷凍の必要がないので、輸送時のエネルギーを抑えることができる。また、生ごみも出さずに容器はリサイクルできる。食品の安全や環境保護が叫ばれている今日、食料缶は社会のニーズに幅広く応える食材と言える。
皮なしミカンは日本が発明!~さまざまな缶詰の技術
シンプルに見える缶詰だが、さまざまな技術や工夫が詰め込まれている。その一部を見てみると……
(1)ミカン
ミカン缶詰は日本オリジナルの製品だった。最初は外皮のまま丸ごと詰めてシラップを入れていたが、試行錯誤の末、1927(昭和2)年に薄皮を剥がす技術が実用化された。
(2)グリーンピース
特殊な方法によりエンドウ豆の葉緑素を豆に定着させ、色鮮やかなグリーンピースを実現したのも日本が生み出した製法である。
現在では、上記のミカン缶、このグリーンピース缶とも、日本の製法が世界の標準技術になっている。
(3)フルーツみつ豆
夏の風物詩フルーツみつ豆。寒天と赤エンドウには熱に強い細菌が存在するため高温殺菌が不可欠だった。
そのため、寒天については、まず溶かした状態で高温殺菌してから冷やして固める。一方、赤エンドウは個別に高温殺菌しておく。そして寒天、赤エンドウ、フルーツ類一式を缶に充填してから、缶ごと低温殺菌するという二段階殺菌の方法が採用されるようになり、フルーツみつ豆缶の製造が可能になった。
(4)桃
白桃は缶詰加工する4、5日前に収穫され、工場で完熟を待って加工する“追熟”という工程が組み込まれている。この期間に水分が蒸散して甘みが増し、上品な香りととろけるような舌触りが生まれる。輸入品は追熟工程が厳密でない物が多い。ちなみに黄桃は追熟しても甘みや硬さの変化が少ない品種のため、追熟せずに加工されている。
以前は缶切りがないと開けられなかった食料缶。最近は簡単に手で開けられるタブリング付きの製品が増えている。また、シラップや調味液が入っていないドライパック(または高真空缶詰)と呼ばれる商品も増えている。非常に高い真空下で密封して加熱殺菌する技術で、これにより大豆やスイートコーンなど素材本来の味や歯ごたえを保つ野菜缶詰や、焼き魚やきんぴらごぼうなどの惣菜缶詰が可能になった。また、缶全体の軽量化にも寄与している。
これまでも、これからもスタンダード
現在、世界で作られている缶詰は約1,200種類。日本では約800種類が作られている。一見、定番に見える食料缶にも、さまざまな技術やアイデアが導入され、より美味しく、使いやすくなっている。今後も社会のニーズに合わせて進化しながら、常に私たちの生活に溶け込んだ存在であり続けるだろう。
一方、食品を保存する缶の素材や製缶技術も進化を遂げている。鋼材面では、人体への影響はもちろん、環境負荷軽減も視野に入れた新しい鋼材の開発や、中でも軽量化と強度を両立させた薄肉化などの技術躍進が挙げられる。一方、製缶技術では、蓋、胴、底の3つのパーツから作る「3ピース缶」に加え、蓋とカップ状に成形した1枚の鋼板の2つのパーツを使い、缶胴部のハンダ付けや溶接などの工程を省略した「2ピース缶」が開発された。強度の高い3ピース缶は真空度の高い食品缶に使われるなど、用途に合わせた製缶方法が選ばれている。
また、2ピース缶の外面印刷においては、缶に直接塗装・印刷する方法に加え、印刷したポリエステルフィルムを缶胴に貼り付ける「ラミネート」という画期的な技術が発明され、緻密な印刷表現を要するデザインが可能になり、塗装・洗浄時の省エネルギー・節水、製造時間の短縮につながった。
消費者ニーズが多様化する中、製缶技術の進歩やバリエーションは、缶詰の可能性を広げ新たな商品開発に貢献している。進化する食品技術とともに、より安全に、より高品質に食品を提供する挑戦は続く。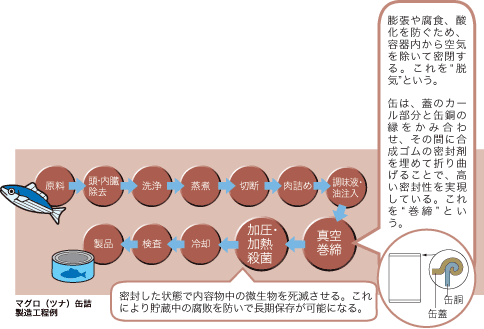
:参考資料:
(社)日本缶詰協会編「缶・びん詰、レトルト食品のすべて(日本食糧新聞社)」、「冒険缶詰(ワールドフォトプレス)」
ミカン缶詰は日本オリジナルの製品だった。最初は外皮のまま丸ごと詰めてシラップを入れていたが、試行錯誤の末、1927(昭和2)年に薄皮を剥がす技術が実用化された。
特殊な方法によりエンドウ豆の葉緑素を豆に定着させ、色鮮やかなグリーンピースを実現したのも日本が生み出した製法である。
現在では、上記のミカン缶、このグリーンピース缶とも、日本の製法が世界の標準技術になっている。
夏の風物詩フルーツみつ豆。寒天と赤エンドウには熱に強い細菌が存在するため高温殺菌が不可欠だった。
そのため、寒天については、まず溶かした状態で高温殺菌してから冷やして固める。一方、赤エンドウは個別に高温殺菌しておく。そして寒天、赤エンドウ、フルーツ類一式を缶に充填してから、缶ごと低温殺菌するという二段階殺菌の方法が採用されるようになり、フルーツみつ豆缶の製造が可能になった。
白桃は缶詰加工する4、5日前に収穫され、工場で完熟を待って加工する“追熟”という工程が組み込まれている。この期間に水分が蒸散して甘みが増し、上品な香りととろけるような舌触りが生まれる。輸入品は追熟工程が厳密でない物が多い。ちなみに黄桃は追熟しても甘みや硬さの変化が少ない品種のため、追熟せずに加工されている。
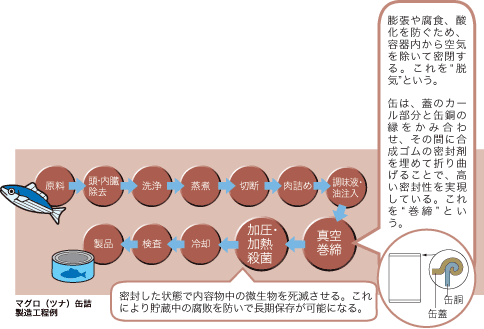
(社)日本缶詰協会編「缶・びん詰、レトルト食品のすべて(日本食糧新聞社)」、「冒険缶詰(ワールドフォトプレス)」

